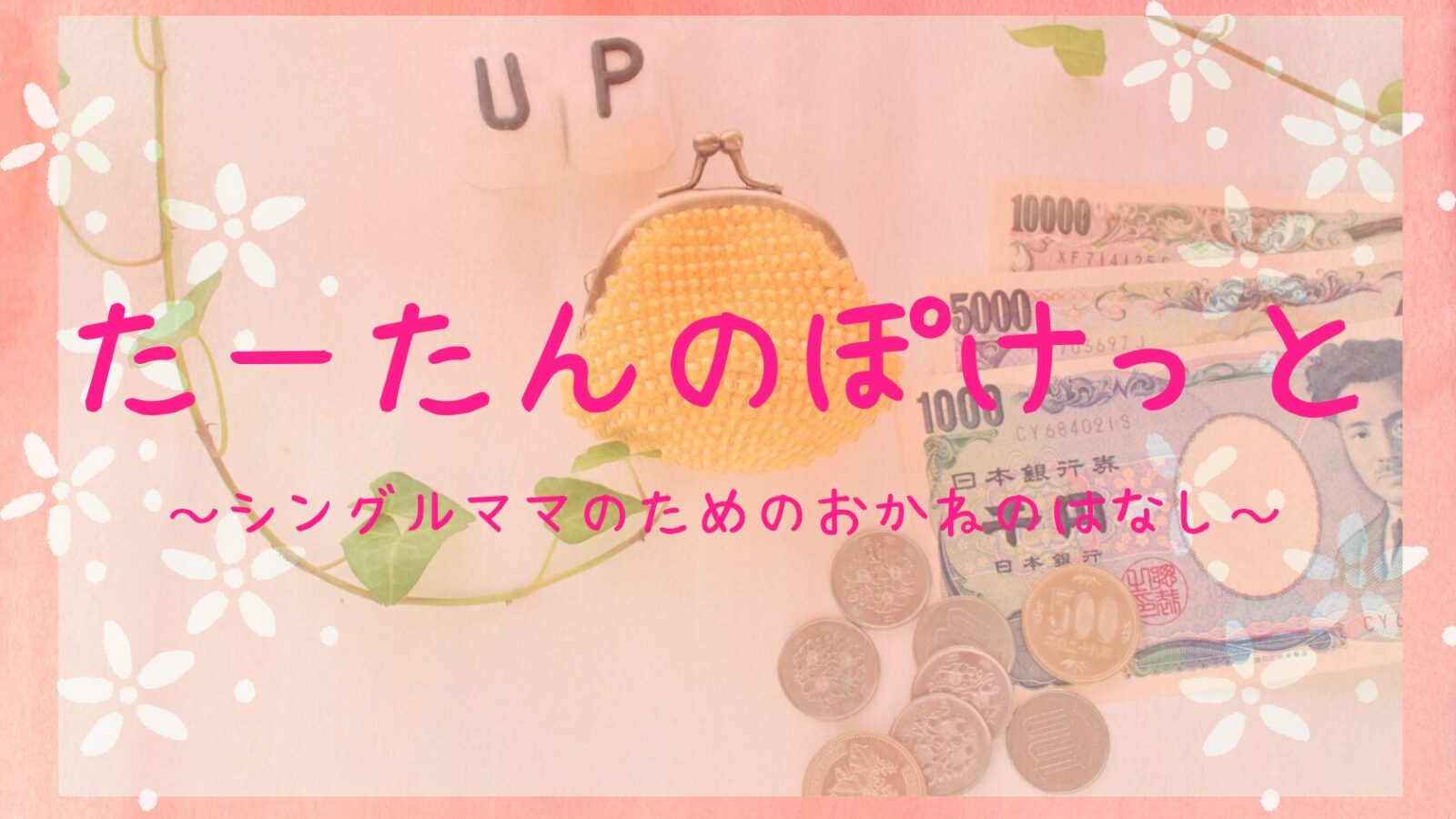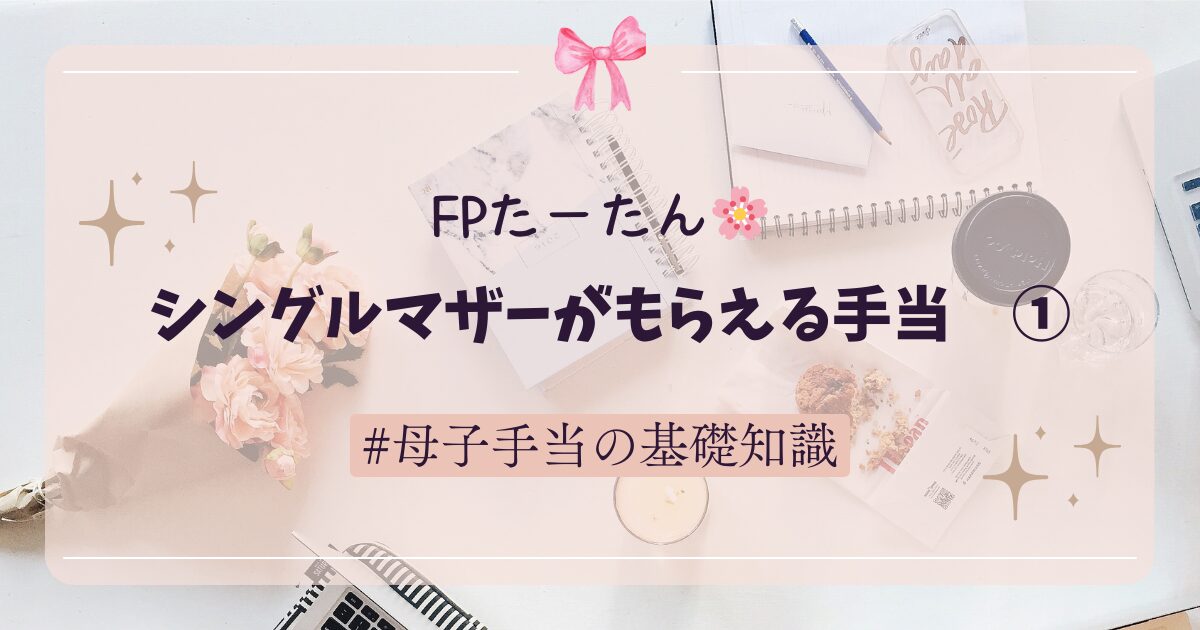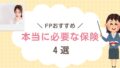未成年のお子さんが居て離婚や死別などで母子家庭になった場合…
ひとりで子どもを育てていくことに不安が募るものです。
「母子家庭」「ひとり親」と聞くと経済的な負担を一番に心配することが多いのではないでしょうか。
ただ、国の制度としてひとり親向けに様々な助成制度や減免制度が用意されています。
制度が難しくてややこしいですよね。
今回はそういった不安を少しでも軽くなるように
分かりやすく母子手当の基礎知識についてまとめていきたいと思います🌸
現在、ひとり親の方や離婚を考えている方に貢献できればいいな、と思っています。
母子手当の基礎知識
ひとり親やシングルマザーになったからと言っていたずらに不安になることもありません。
シングルマザーが活用できる助成制度や減免制度は様々用意されています。
どんな制度があるのかを賢く知って活用していきましょう。
母子手当とはひとり親などの養育者に支払われる手当
母子手当とはひとり親などの養育者に支払われる手当のことを言います。
いわゆる「児童扶養手当」と呼ばれるものです。
この制度は、離婚や死別などの理由で父母と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立を促進することを目的としています。
正式には「児童扶養手当」と呼ばれ、母子家庭だけでなく、父子家庭や祖父母が養育する場合にも適用されます。
簡単に言うとひとり親になってしまったお母さんだけではなくて、親権を引き取ったお父さんや場合によっては祖父母にも支給される手当のことを言います。
受給要件
母子手当には支給要件があります。
- 離婚や死別により、父または母と生計を同じくしていない児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)
- 養育者が父母に代わって児童を養育している場合(例:祖父母)
支給対象者は、児童を養育する母親、父親、またはその代わりに養育する者です。
母子手当は、生活の安定を図るための重要な経済的支援となります。
受給額
母子手当の受給額は、家庭の所得や養育する児童の人数によって異なります。
2024年度の支給額は以下の通りです。
- 児童1人目: 月額最大45,500円
- 児童2人目: 月額10,750円(加算)
- 児童3人目以降: 月額6,450円(加算)
この手当は、所得制限が設けられており、一定以上の所得がある場合は支給額が減額されるか、支給されないこともあります。
具体的な所得制限は、扶養親族の数に応じて異なります。

公的支援制度についてのまとめ記事があるのでそちらも一緒に参考にしてね🌸
受給額の計算方法
では、実際にどのぐらいの金額が母子手当としてもらえるのか…ということが気になると思います。
受給額がいくらになるのかはいくつかのポイントがありますので記事を読んで参考にしてくださいね。
1.受給資格者の所得確認
児童扶養手当はママやパパ、いわゆるひとり親が働いてきた前年度分の所得に基づいて決定されます。
給与所得者…いわゆる会社に勤めている人というのは源泉徴収票を頂くと思います。
その記載の中に
「給与所得控除後の金額」
というものがあるかと思います。
この金額を元に手当の「全部支給」か「一部支給」もしくは「支給停止」なのかが分かる…ということになります。
2.受給額の計算方法
全部支給と一部支給には違いがあります。
受給資格者の所得が一定限度額を下回る場合…全部支給
限度額を超える場合…一部支給もしくは支給停止
この支給額の差に関しては所得制限によるものが大きくかかわってきます。
2024年度版ではありますが、一部例として表を記載します。
あくまで参考程度としてみていただけると幸いです。
◎満額支給額(2024年度)
| 子どもの人数 | 月額支給額 |
|---|---|
| 1人 | 44,140円 |
| 2人 | 54,560円(+10,420円) |
| 3人 | 60,810円(+6,250円) |
| 4人目以降 | 1人増えるごとに +6,250円 |
◎一部支給額(所得に応じて減額)
3人目以降の加算額:6,250円 ~ 3,130円
計算式:
43,130円 -(所得額 - 所得制限額)× 0.0230559
※ 計算結果の端数は10円未満を四捨五入
2人目・3人目以降の加算額も、所得に応じて減額されます。
2人目の加算額:10,420円 ~ 5,210円
上記のような複雑な計算をして受給額を出していくわけですが…
気になるのは、受給額を決めるための計算式…
43,130円 -(所得額 - 所得制限額)× 0.0230559
この赤字の所得制限額かと思います。
いくらまで働けば受給できるのよ‥‥と、たーたん自身もいつも気になっていました。
3.所得制限額
◎所得制限額
✔ ひとり親本人の所得が、以下の基準を超えると満額 or 一部支給が変動
✔ 所得 = 収入 - 給与所得控除 - 各種控除(扶養控除・社会保険料控除など)
令和6年11月からの制度改正による所得制限表
| 税法上の扶養人数 | 受給者本人【注意1】 | 配偶者および扶養義務者【注意2】 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 770,000円 | 2,160,000円 | 2,440,000円 |
| 1人 | 1,150,000円 | 2,540,000円 | 2,820,000円 |
| 2人 | 1,530,000円 | 2,920,000円 | 3,200,000円 |
| 3人 | 1,910,000円 | 3,300,000円 | 3,580,000円 |
| 4人 | 2,290,000円 | 3,680,000円 | 3,960,000円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに380,000円加算 |
- 上記所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
引用:豊島区 児童扶養手当所得制限額表
児童扶養手当所得制限額表|豊島区公式ホームページ
他の自治体でもこのように所得制限表の記載があるのでHPで確認をしましょう。
受給額計算例:
受給額の計を例に挙げてみました。
上記自治体の内容で計算した場合となります。
- ひとり親(子ども1人)
- 税法上の扶養人数:1人
- 所得:1,300,000円
- 各所得制限の目安(令和時点の例)
- 全部支給の所得制限:1,150,000円
- 一部支給の所得制限(段階的逓減開始):2,540,000円
- ※支給停止(=支給対象外)となるのは、2,820,000円以上となります。
- 満額支給の場合の月額(第一子の場合):
約 43,130円(自治体等により若干の差はあります) - 逓減率:
所得が全部支給の制限を超えた場合、超過額に対して 0.025(2.5%)の率で月額から減額する仕組みです。
【計算手順】
- 超過額の計算
所得が全部支給の制限額(1,150,000円)を超えた分を計算します。
1,300,000円−1,150,000円=150,000円 - 減額される金額の計算
超過額に逓減率を乗じます。
150,000円×0.025=3,750円 - 一部支給額の計算
満額支給時の月額(43,130円)から上記減額分を引きます。
43,130円−3,750円=39,380円
この例の場合、ひとり親(子ども1人)の所得が1,300,000円の場合、児童扶養手当は月額約39,380円の一部支給となります。
まとめ
児童扶養手当の受給額は、所得制限の計算やもろもろの控除額に逓減率というなんとも素人にはわかりにくい数字を用いて計算されます。
受給額の正確な金額については各自治体に相談していくことが良いと思われます。
どのぐらいの収入であれば、児童扶養手当を受給できるのか…ということに関してですが、
収入ベースで
年収200万円前後で満額、365万円以上で支給なしになるイメージ
このように年収計算をしていくと分かりやすいです。
扶養人数や控除によって所得制限額や受給額が変わってしまいます。
上記の内容はあくまでも概算例となります。
正確な金額に関しては各自治体の公式シュミレーションや窓口での確認が必要となります。

ご参考にしていただけると幸いです!